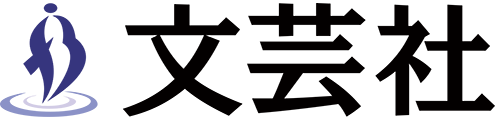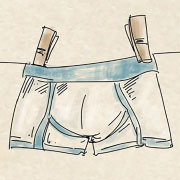���X�̐��E�ɖ�����ꂽ�̐l����
�F���B���グ��Ζڂɂ��f��̂ɉʂĂ��Ȃ������A�n����́u���E�v�Ƃ����ꂪ��������I�ȁg�����h�Ƃ͂܂������ʂ́A�����̍L�����������g�ǂ����h�̐��E�\�\�B���X�����߂��A�_��I�Ń~�X�e���A�X�Ȗ��m�̖��f�ɖ������F���́A�l�X���䂫���Ă�݂܂���B
�u�^���Ȃ����Ȃ����̑��̒��Ɍ�Ɍ����ЂČ��鐯����v
�Ɖr�����̂͐����q�K�ł����A����ɖ��������͍̂�Ƃ�w�҂������܂���O�ł͂���܂���B�������Ȃ���A�u���}���e�B�b�N�Ȑ��ˁv�u�����ˁc�c�v�ƁA�����Ƃ肵���፷���łӂ��茨���ׂ邱�Ƃz�������Ȏ������ƈ̐l������I�ɈႤ�̂́A���̐q��Ȃ炴��O�ꂵ���X�|�Ԃ�ł��B��ʐl���V������낵��������������i�ɐ����A���������������o���u�Ƒ�����̂Ƃ͋t�ɁA���̐��E�́g�{���h�����́A�V�ɕ����Ԑ��X��������i�Ƒ����A�Â��_�Ԃ����߂���T���܂��B�n�����܂ސ��X������F���ɂ́A�b�q���߂��[���Ȏv�z������A�l�Ԃ̎p����j���f�������w��̓y�낪����\�\�����M���A�I���̂Ȃ����Ԃ��₵�āu���݁v�̈Ӗ���T�����Â��Ă����ނ�̎p�����Ă݂܂��傤�B
�I���I������������u���̘a���v�����̕�
���{�Łu���v�ɂ܂��w��Ƃ����A�����ɂ��̖������т��͖̂�K���e�i�̂���ق������j�ł��傤���B20���I�����܂ŁA���{�ł͐��ɓ��ꂳ�ꂽ�a�����Ȃ��A���ɂ܂��ŗL�̓`���Ȃǂ��Ȃ��ƍl�����Ă��܂����B�����A�w�K���̕ҏW�҂ł��������e�́A���̒ʐ��ɋ^�������A�S���ɌĂт����Đ��̘a�����W���n�߂��̂ł����B���̌��ʁA�c��Ȑ��̃f�[�^���~�ς���A���̌Ăі��▯�b�`���̒n�搫�E�A�������炩�ɂȂ�A�̌n���Ă��_�Ƃ��Ă܂Ƃ߂�܂łɎ���܂��B���e���ނ����̓���̂��Ƃ��u�V�������w�ҁv�ƁA���܂蕷������Ȃ������ŌĂ�鏊�Ȃł��B
�y���́A���̉Ă���̎R�r���ɂ��āA�ǂ���ƗJ�T�ȃ��m�N�������点�Ă���B�܂��������̐��̕\��͐̂̐��肢��`�����܂ł��Ȃ��A�N�̖ڂɂ��O���[�~�[�ł���B����ǁA��x�������]�����ł�������ƁA�ނ͂����܂��A���̗J�T�����̂ĂāA���̐��E�ɂ���������̊�ς������Ă����B
(�w��K���e�@���͎���x���}��/2015�N)
���e�̐��ɑ��鈤����������ɂ́A�u������ꂽ�v�Ƃ����悤�ȏ�I�ȕ\�������A�u�D���ōD���ł��܂�Ȃ��I�v�u�l�Z�����ڂ������Ȃ��I�v�Ɛg���悶���Ďv���̏��\���悤�Ȑ��i���j�̂܂܂̌��t�������킵���ł��傤���B���N���ォ���Ȗ�Ȑ�������������e�́A�����Ƃ��������Y�ꂪ�������̎p�\�\����́A�I���I�����ł����B���w����A�C�w���s�̂��Ȃ��}�a�ɓ|�ꂽ���e���N���A�a���̑�����ЂƂ茩�߂����ł��B
�����m�炸�ɎY������������ɂ��A���̗Y��ȕ�ʂ̐}�͉����̏�̋�ɕ`����Ă����B�����āA�₪�Ğl�ɓB�̋�����̋�ɂ��A���ꂻ������̓V�}�͎Wࣁi������j�ƋP���Ă���B
�i����j
����̂悤�ɐ��߂�l���𑗂������e�́A1977�N�ɐ�������܂��B10�Έȏ�̗��ꂽ����̑�Ŏ��Y��蒷�������A�����̕��ώ�����y���ɒ�����92�Ƃ��������ł����B�I���I�����ɑ��I���ЂƂ����Ȃ�ʈ�����������V�������w�҂��A�|���l�V�A�l�ɕ���āA����s���������Ƃ��ċ������̂��I���I�����ł����i�|���l�V�A���Z���͎��̏��Ŏ���ɏZ�݂��������w�����Ƃ����j�B����Ȍ��t���c�����e�͐��ƂȂ�܂����B
�u�ڂ��̍��͂ˁA�I���I�����̉E�[�ɎT���Ȃ����v�B
�F�����Î����u���݁v���v�����Â������J�Y��
�����ƁE�v�z�Ƃ̏��J�Y���́A�咷�ҏ����w����i���ꂢ�j�x��50�N�ԏ����Â��A�\�z���10�͂ɋy��9�͂܂ŏ����グ���Ƃ���ő��E���܂����B�u���ƉF���̓���Ƃ����߂ɁA�����͐��܂ꂳ����ꂽ�A�ƁB���w������������Ă����̂͂����������ƂȂ�ł���v�ƌ�������J�B���̌��t�̐�ɂ�����̂������L���̈��w����x�A�����āA�F���̃C���t�B�j�e�B�Ɛ��̖��z�ł������Ǝv���܂��B�����̏����Ƃَ͈��̐��E���J���Ă݂����v�ُ����w����x�ɂ����āA���J���Nj����Â����̂́g���݁h�Ƃ������Ƃ̈Ӗ��B���̂Ȃ��ɁA�F���_�������オ��܂��B
�c���F���Ƃ����Ă������͐��S���N�B�����ɔ�ׂ�Ώu�Ԃɂ����Ȃ��B����ɂ���ɏu�Ԃɂ����Ȃ��l�Ԃ����F���̐��S���N����������Ɍ���Ȃ���A���_�̓O�ꐫ�͂Ȃ��B
�i���J�Y���w����V�x�u�k��/2003�N�j
���������u���b�N�z�[���̂��Ƃ��[���ɉ䂪�g�߂đ��݂Ƃ͉����Ǝv�����A�w����x�Ƃ����ٌ`�̏����̎��M�ɔ��������������J�Y���B����������ȏ��J�ɂƂ��āA�F���Ƃ́A�����߂炵����������˂Ȃ�Ȃ��ΏۂƂ����킯�ł͌����ĂȂ������悤�ł��B��K���e���I���I�����Ȃ�A���J�Y���̓A���h�����_���_�B�~�������͉̂����Ɩ���u�Í����_�v�A�D���ȐE�Ƃ́u�F���肢�t�i���������E�Ƃ�����Ƃ��āj�v�Ɠ����A��Ƃ̓I�y���O���X�ŃA���h�����_���_�߂�̂�閈�̓��ۂƂ��Ă����̂ł����i���J�̖����́u�A���h�����_���v�Ɩ�������Ă���j�B
���ɂƂāA�F�����s�Ƃ��������ȉA�Ȃɕx���t�̋����́A�����ɘf���Ԃ���łȂ��A���B�̑��z�������𑖂Ă����͐��_�̈�{�̘r�̂͂��܂ōq�s���Ă䂫�A����ɂ�����������̈Í��̋�ԂɎ��B�̑o���̌Z��̂��Ƃ��ɑs��ɐ��Ă���A���h�����_���_�ڎw���Ĕ��ł䂭���_�Ԕ�s�ɂ܂ŒB���Ȃ���A�[���Ɍ����\���ꂽ���̂Ƃ͂����Ȃ��i�����j���B�����B�́u�F�����s�v�ʼn��������Ȃ������Ԃ́A�F���ɂ��ĉ�����z�����A���_�̕s�v�c�ȍL�傳���o������̂��[���߈��̋�ɂ�������قǁA�����A�������̂ł���B
�i���J�Y���w�s�����䂦�Ɍ�M���x����v����/1975�N�j
���͂������c�c�Ƃ��̑O�ɁA���X�ƌ������Ă݂悤�B
���́w�s�����䂦�Ɍ�M���x�̈�߂́A���J�Y���̃A���h�����_�ւ̈��ƈ،h���������̂ł���A�܂��A�F���̂Ȃ��ɑ��݂���l�Ԃ����ׂ������ɕx���b�Z�[�W�Ɠǂނ��Ƃ��ł��܂��B�C�k�̏�Łu�V�N�̊v���Ƒn���v�ɂ��ĔM����������J�Y���́A�V���ĂȂ��G�l���M�[�ɖ��������Ă��܂����B�v���A��K���e�݂̂Ȃ炸�A�c�����狕����Ă���ꂽ���J�Y�����A�J���Ă݂��90�߂�������S�����Ă��܂��B���₻��ǂ��납�K�����I�E�K�����C�����āA16�`17���I�̐l�ԂƂ��Ă͋����ׂ�80�Ɏ肪�͂��Ƃ����������ւ����̂ł��B������A���Ƃ̌�����p�������������炷�H�\�\�\����������z�����点�邱�Ƃ��A��������y�����ł͂Ȃ��ł��傤���B
����������z���A�G�ƕЂÂ��Ă͂����܂���B�Ђ���Ƃ���ƁA�F�������������ׂĂ̐l�X�ɕ����Ă��関�m�̃p���[��ے肵�Ă��܂����Ƃ����A�펯�Ɏ����_����������v�l�n�т̎��p�ւ̓�����ɗ��s�ׂƂ�����̂�������܂���B�F���ɂ́A�_��̋P�����Ƃ炵�������͂�����\�\��ƂɂȂ肽���Ȃ�A���X�̏u����ɂ͂���Ȃӂ��Ɏv���ɒ^���āA�ЂƂ�Â��ɍ��ɂ̋�����グ�Ă݂�̂��ꋻ�ł��B���Ȃ��̕��͂����߂�����A������Ƃ����]�@���K��Ȃ��Ƃ͌���܂���B