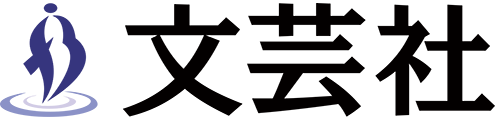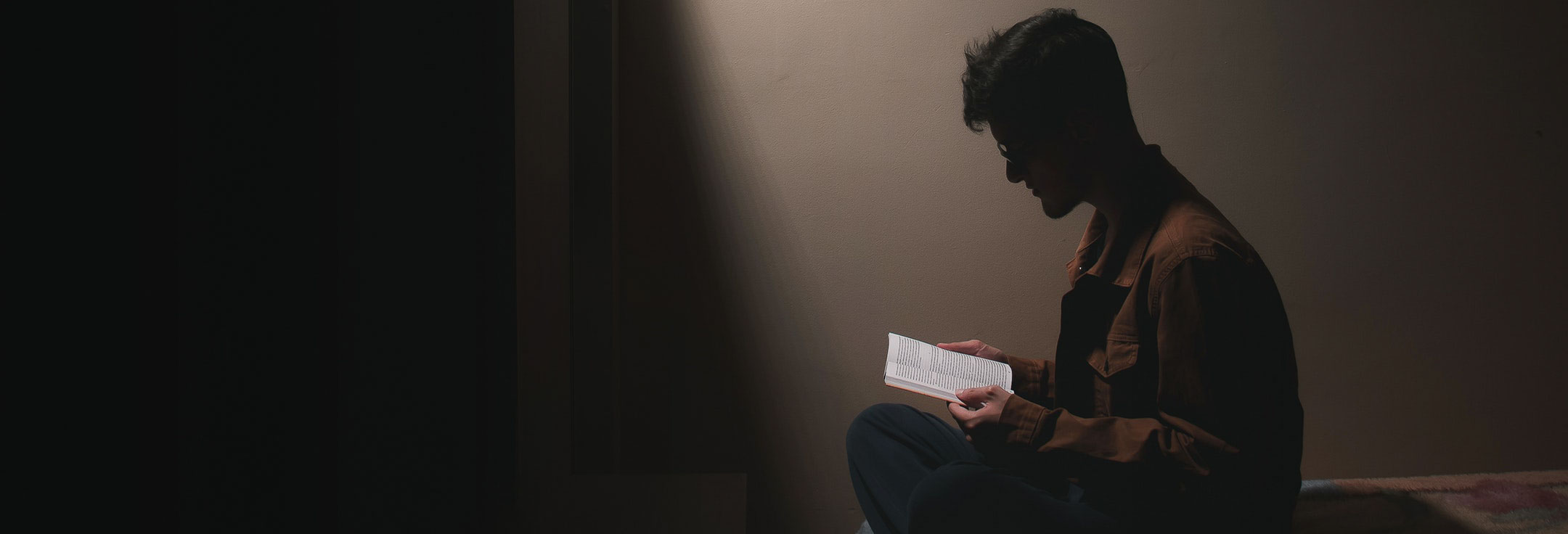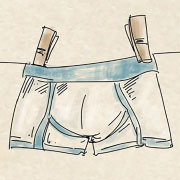�u����v�A����͏����Ȓm�ƋZ�ƍ��̌���
�N�����Ƃ��������č�ƂɂȂ�A�����̖{���o�ł���I�@�ƕs�ޓ]�̌��ӂ��ł߂��F����̂Ȃ��ɂ́A���ӂ͂��ǁA���܂��L�O���ׂ����삪�����オ���Ă��Ȃ�!!�@�Ƃ����������������邱�Ƃł��傤�B�����A�ł͉����������Ǝv���Ă��܂����H�@�ܑ_���̑�ށH�@�܂��͘r�����H�@�Ƃ肠�����g�߂Șb�������Ă݂�H�@�m���ɂǂ�ȓ��@�������ʕM���������Ă����̂ł������͂���ł��肪�����̂ł����A������Ƃ����͐T�d�ɁB�Ƃ����̂�����Ƃ́A��ƂƂ��ăX�^�[�g���ɂ�����A���ɂ������đ厖�ȍ�i�ɂȂ�̂ł��B����ӂ�ȑԓx�Ŏ��g�ނ̂ł́A��Ɠ��ɂ݂������T����u���̂Ɠ������ƁB�u����v�Ƃ́A��ƂƂ��Ă̈ꗢ�ˁA�����ł�����肩�A�ЂƂ�̐l�ԂƂ��Ă̍����������_�Ȃ̂ł��B�����炱���A�^�ɏ����������́A�����Ȃ�������Ȃ���ނ�����Ȃ���Ȃ�܂���B���ɉ��߂Ă����A���邢�͐S�̉��ɖ����Ă���A�C�f�A����ĉԊJ������B����������Ƃ������Ƃ́A���̂܂��ƂȂ��@��Ȃ̂ł��B�����炱�����������˂Ă���̂��I�@�Ƃ�����������������ł��傤�B�ł��A�����A����Ő����Ȃ̂ł��I
���w�j�ɖ������������̐�B�B�ނ�ɂ��Ă�����́A��Ɛl���ɂ����āA�܂����̐��U�����ɂ����āA�傫�ȈӖ��Ɖ��l�������ē��ʂȋP�������܂ɓ`���Ă��܂��B�����ނ炪�A����ɌȂ̒m�ƋZ�ƍ��𒍂����܂Ȃ�������A�̂��̖����⎖�т��z�������ǂ�������^��ł��B�������A���삪���̂��Ƃ��Y�ꋎ��ꂽ��]������Ȃ�������Ƃ�����ł��傤�B�������A����ȑ��삾�Ƃ��Ă��A���̏�����ɂƂ��ĈӖ��̂Ȃ����̂ł��������Ƃ����A�����͔ہB���Ƃ����n�A�������Ȃ��̂ƐU��Ԃ邱�Ƃ͂����Ă��A����̑��݂̉��l���A���̈Ӗ����A�N���m��Ȃ��Ă���Ɩ{�l�͋��Ɋo���Ă���͂��Ȃ̂ł��B
�u����v�̈Ӗ��Ɖ��l�͒N����Ǝ��g���m�����
���삪�]������ʂ܂ܖ�����Ă����c�c����͈����ł��B����������ȗ��_���ׂ����Ԃ́A�Ƃ��Ƀm�[�x���܍�Ƃ̐g�ɂ��K��܂��B�암�A�����J��Ƃ�����Q�̏����ɂ���ăm�[�x�����w�܂���܂����E�B���A���E�t�H�[�N�i�[�B���̒��ґ���́w���m�̕�V�x�ł����A�푈�ŋL�������������N����l���Ƃ��邱�̕��ꂪ�Ƃ肽�ĂĒ��ڂ���邱�Ƃ͂���܂���ł����B���������̍�i�̒n���Ȃ����āA�̂��̉ˋ�s�s�u���N�i�p�g�[�t�@�v��Ƃ����T�[�K�A�푈�ɂ���ĉ����������j�ł��Ă�����Ƃ̕���w�T�[�g���X�x��A��k�푈�̉p�Y�ꑰ�̖v�����a�V�Ȏ�@�ŕ`������\��w�����Ɠ{��x�͐��܂�Ȃ������ł��傤�B
�������암�A�����J���\�����Ƃ̂ЂƂ�Ƀ}�[�K���b�g�E�~�b�`�F�������܂����A�������̂Ƃ���ޏ������O���\�����̂́w���Ƌ��ɋ���ʁx������삾���B���E�I�x�X�g�Z���[�ƂȂ������̏����́A�Ђ���Ƃ���Ƒ傫�������̂�������Ȃ�������ޏ��ɂ����炵�A�������v���C�o�V�[�̑r���ɓ��h�����~�b�`�F���́A����Ɏ����߂邱�ƂȂ���������A���쌠�N�Q�Ƃ̓����ɖ�N�ƂȂ���X�𑗂�܂����B����ǁA���܂Ȃ��d�b��A���m��ʐl����̈����T�C���U�߂ɋ�����Ȃ����ޏ��ł������A�������ړx�����ɂȂ�Ƃ���͂���ŕs���Ɋ�����悤�ɂȂ����悤�ł��i�A���E�G�h���[�Y���w�^���ւ̓��\�}�[�K���b�g�E�~�b�`�F���̐��U�x�j�B�V�̎S�A�Ƃ����������ƕ��G�Ȑl�ԐS���ɊW����S���̕ω��ł����A������ɂ��Ă��~�b�`�F���ɂƂ��āw���Ƌ��ɋ���ʁx���A���������Ȃ���ȍ�i�ł��������Ƃ̏Ƃ�������G�s�\�[�h�ł��B�l�������킷�قǂ̔ς킵�����������炵���ɂ���A����ŁA�l�X�Ɍ����ĖY��Ăق����͂Ȃ��B�ꖳ��̍�i�ł������ɈႢ����܂���B
�������W�o�łɌ��������̗L�����l�̎v��
���삪��Ƃ̃I���W���ł���̂́A�����ƂȂ炸�Ƃ����l�ł����Ă��������ƁB���⎍�l�̂ق������������A����𐢂ɏo�������A�o�ł������Ɗ肤�C�����͐؎��ł�������������܂���B�����뎍�W�̏��Əo�ł̓���͂ނ����������A�Ƃ������A�������W�𐢂ɏo�����Ƃ���Ȃ�قڎ���o�ł�����i�͂Ȃ������̂ł�����B30�Ś�܂������l�̒��������350�т��܂�̍�i���c���܂������A���O�o�ł��ꂽ���W�́w�R�r�̉́x�������i����܂��Ȃ��w�݂肵���̉́x�����s�j�B������́w�R�r�̉́x���A��ɘR�ꂸ����o�łł����B�����Ɏ��铹�ɂ��Ă������łȂ��A�����W�߂ɖz��������A�����o���Ă��ǂ�������ł��܂����낤�ȂǂƋ^�������Ďv���ɔC�����A����2�N���܂�̌������₵�Ă��܂��B������1934�N12���A�悤�₭�w�R�r�̉́x�����s����܂��B����͎Ⴂ����3�N�O�̂��Ƃł����B
�w���̂��̐��x
�i�O���j
�l�͉��������߂Ă��A�₦�����������߂Ă��B
���낵���s���̌`�̒��ɂ����A�܂����낵���܁i���j��Ă��B
���̂��߂ɂ͂͂�A�H�|�����|�����ĂȂ����@���ł��ւ���B
�������A���ꂪ�����͕���Ȃ��A�Ђ��������߂��͂Ȃ��B
���ꂪ�����Ƃ͎v�ւȂ��A������ł���Ƃ͎v�ӁB
���������ꂪ�����͕���Ȃ��A�Ђ��������߂��͂Ȃ��B
����ɍs�������ꂩ�����̕��r���ցA���F�i������j�������߂��͂Ȃ��B
���Ɏ����𝈝��i���炩�j�ӂ₤�ɁA�l�͎����ɐu�i���j���Ă݂�̂��B
����͏����H�@�Ái���܁j�����̂��H�@����͉h�_���H
����ƐS�͋��Ԃ̂��A����ł��Ȃ��A����ł��Ȃ��A����ł��Ȃ�����ł��Ȃ��I
����ł͋�̉́A���A����ɁA������̉̂Ƃł����ӂ̂ł��炤���H
�w�U�x
�ۉ��i���Áj��Ƃ��ւ���͂��ӂ��Ƃ̏o���ʂ��́I
��Z���ɁA���ɐ����������Ȃ�Ƃ͂��ӂ��̂́A
�����Ȃ��o���ʂ��̂ł�������A�䂪���͐�����ɒl�Ђ�����̂ƐM����
����挻���I�@����Ȃ��K���I�@����͂���̂͂���͂�܁T�ɂ悢�Ƃ��ӂ��ƁI
�i�㗪�j
�i�w�������玍�W�x����/��g���X/1981�N�j
��������͕��G�ȁA�����������i�����l���ł������悤�ł��B�_���ƌĂꂽ�c������A����͐ܟB�Ȃǂ��Č������^�������A�ߕی�Ȗʂ�����A����ւ̈���Ɣ����S�A�Â��Ƒa�܂����A�������������銴��͐₦������̓��ʂɓ��荬�����Ă����Ƒz������܂��B���Ƃɐ�����𗊂�A�o�Ŕ�p�S����_���l�Ԃ̈�ʂ����̂�����Ȃ�A���g�̎�ɂ��|�W�i�w�����{�I���W�x�j�����s������A���e�݂̂Ȃ炸�e�ʂƂ����e�ʂɑ��錒�C���Ől�𖣂���̂�����ł����B�e���̂������͏�O���Y���S���́A���������Ȃ炴��A���������b�ɕ��������Ă��܂��悤�Ȑl�Ԃł������Ƃ��̈�ۂ��L���Ă��܂��B������A��������ꂽ��������B���������߁A�����̓�����T���Â������̐S�̋O�Ղ��A�w�R�r�̉́x�ɂ͍��܂�Ă��܂��B
�u����v�Ƃ������̔�ɍ��ތ��t�́c�c�H
�u����v�Ƃ́A��ƂɂȂ肽���҂��Ӑg�̎p���������ėՂނׂ�����̔�ł��B���̔�������̉Ƃ̒��x�����_�ɂ��傱��ƌ�������ȂǂƂ������Ƃ́A�l�����Ȃ��ł��傤�H�@�u�{�v�Ƃ����`�ɂ��ďo�ł��Ă����A���ɏo���Đl�̖ڂɐG��Ă����A���X����蕶�����荞�܂�A�����ւ̓����꓾��̂ł��B����ȏd�v�ȍ��̈�삪�A�܁A����Ȋ����łǂ����ȁH�H�@�݂����ɃC���X�^���g�Ȏd�オ��ōς܂���Ă悢���̂ł����B�K�삾����ƁA���܂܂��ɂ���Ȋ����ŏ����͂��߂Ă���ł����āH�@�ł����炷���ɕM��[���A�����Ɖ䂪���ɖ₢�����Ă݂Ă��������B�����͂��̑n��ɉ������߂Ă���̂��A�킩��Ȃ��Ƃ��A�T�����߂�Ӗ��͕K������܂��B�����Ă��̖₢�͂�����A�����͉������悤�Ƃ��Ă���̂��A������������𐬂����Ƃ��鎩���Ƃ͉��҂Ȃ̂��H�@�Ƃ����₢�����ɍs��������܂��B���������҂��Ȃ�ĒN�ɂ��킩��܂���B���҂ł��Ȃ����炱���A���̐��̒��ʼn��҂��ɂȂ邽�߂ɁA�����𐬂����Ƃ��Ă��邱�Ƃɂ₪�ċC�Â����Ƃ��A���Ȃ��ɂƂ��Ắu����v�̉��l�ɋC�Â��͂��ł��B���Ղɏ����グ�Ă͂Ȃ�܂���B���Ƃ����ď����Ȃ��̂͂����Ƃ����܂���B������������҂̂ݒm�鋫�n�ɒH����܂��傤�B���͂�T�ⓚ�̂悤�ł����A���̒T���̓������A��Ƃ�ڎw�����Ȃ��̃I���W���A�u����v�ɒԂ�ׂ����̂Ȃ̂ł��B