本を出版するなら─文芸社。「出版」のこと、気軽にご相談ください。
平日9:30〜18:30通話無料
0120-03-1148問い合わせ
検索
書籍検索
フリーワード検索
ジャンル検索
小説
エッセイ
童話・絵本・漫画
画集・写真集
教育
実用
語学
社会
ビジネス
医学・健康
看護・闘病
伝記・半生記
歴史・戦記
詩集
俳句・短歌
地理・紀行
自然・科学・工業・学術
哲学・心理学・宗教
芸術・芸能・サブカルチャー
スポーツ
雑誌・学参・その他
本を出版するなら─文芸社。「出版」のこと、気軽にご相談ください。
平日9:30〜18:30通話無料
0120-03-1148問い合わせ
検索
書籍検索
フリーワード検索
ジャンル検索
小説
エッセイ
童話・絵本・漫画
画集・写真集
教育
実用
語学
社会
ビジネス
医学・健康
看護・闘病
伝記・半生記
歴史・戦記
詩集
俳句・短歌
地理・紀行
自然・科学・工業・学術
哲学・心理学・宗教
芸術・芸能・サブカルチャー
スポーツ
雑誌・学参・その他
Blog
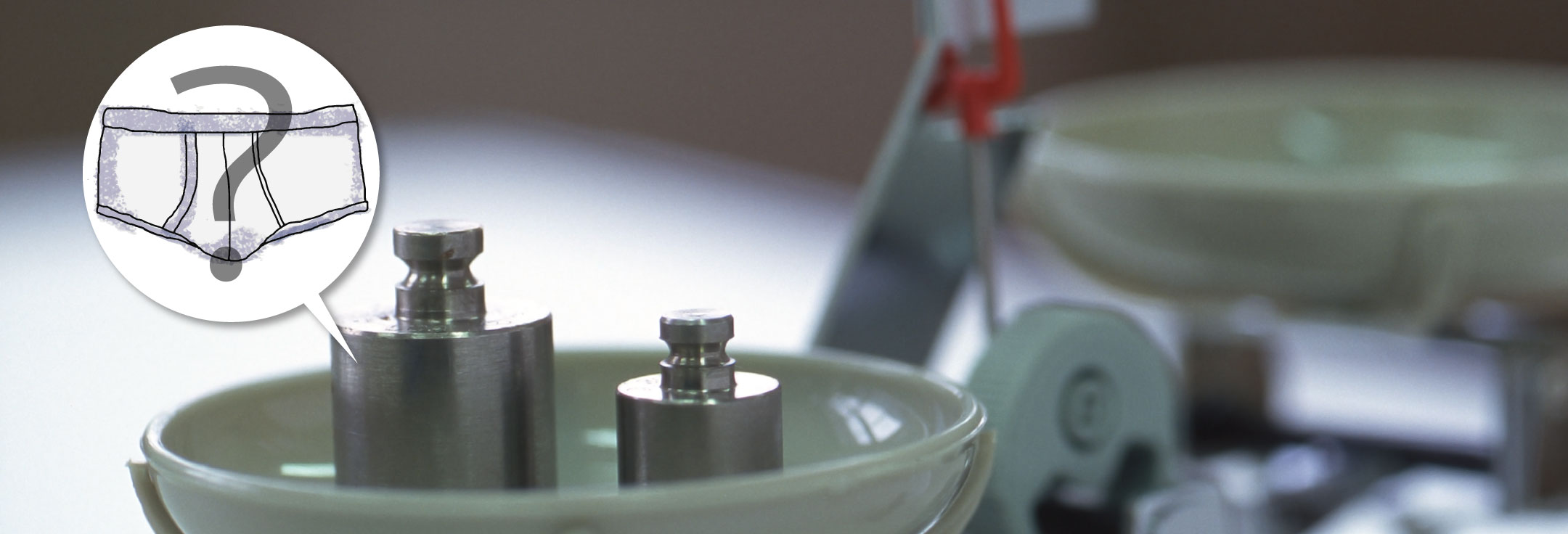
自分にはユーモアがない、とあきらめ顔の人は世間に少なくないようです。ユーモアセンスが完全にゼロという人もまた珍しいので、おおかたは謙遜と見ていいのでしょうが、確かにユーモアは、運動神経同様に生まれもったセンスといえる一面があります。その“センスがない”ということ自体に自覚のない人が、スキーでいうならいきなり上級者コースに入り込み、ただただ転げ落ちるがごとくスベり倒して周囲の寒イボを総立ちにさせる……という場面は往々にしてあります。誰もが人生経験上、その寒さ、またその発生源に自らがなってしまうことの恐ろしさを知っているからこそ、先述の謙遜は謙遜をとおり越して、無用にハードルを上げたくないという思いからくる自衛の域に達しているといえるのかもしれません。まあ確かに、何ごとにおいても身の丈を知るというのは大切なことではあります。
けれど、ユーモアがもし訓練によりレベルアップできるものだとしたら、怖じ気のせいでハナから諦めてしまう姿勢は、作家になりたい者のひとつの可能性を早々に摘み、高みに向かう一路に背を向けてしまうことにほかなりません。何かの分野でひと角の人物になろうとする際に、手持ちの才覚だけで先々まで太刀打ちできるなんてことはまずありません。どんな道も登りのきつい坂道で、一歩ごとに成長していくからこそ、常人では到達し得ない高みに達するのです。とすれば、おれってユーモアセンスゼロだからな……とうなだれて、ユーモア界隈を横目にスルーしてしまうのはもったいないこと。加えていえば、人間関係上のコミュニケーションでのユーモアと、文芸でのそれはまた違います。仮にあなたが自他ともに認めるユーモアセンスとは縁遠い人であったとしても、過去に人を心底笑わせたと思える記憶が皆無だとしても、“文章を書く”という行為においては、そんな日常生活のセオリーの限りではないのです。どうかここはひとつ、これまで眼を背けていたとしても、興味本位でかまいませんので、ユーモア界隈をちょっと覗いてみようではありませんか。
対話のなかで発揮されるユーモアと、文章のなかで光るユーモアとは、少々質と出どころが違うわけですが、じゃあそれはいったいどこに見られるのでしょう? たとえば、コメディのシナリオや漫才のネタは練りに練られたものであるはず。そこに「即興」が差し込まれさらにネタにドライブがかかるのですが、ライブ性を求められることのない文芸を話す上ではいったん忘れましょう。基本的には、シナリオなりネタなりがガッシリと組まれた構想の上を、演者のキャラクターやパフォーマンスが走りまわり「興(=おもしろさ)」を媒介するわけですから、台本とはそうした全パラメータの動きを緻密に計算した上で仕立てられることになります。それはエッセイでも同じ。文章という伝達媒体の特質への心得さえあれば、抱腹絶倒の一篇を書くことも夢ではありません(事実あるのです、電車のなかで読んではいけないほどに笑える本が……)。
そこでまず大事なのが、ユーモアを発する文とはいかなるものかを知ること。文章表現においては、漢字とひらがなの違いであったり、間であったり、比喩の用い方であったり、長文・短文のリズムであったり。また書き手の作品へのアプローチの姿勢でいえば、題材の選択であったりその切り口や掘り下げ方であったり、中途半端を排した無駄と思えるほどの徹底ぶりであったりと、知識と計算と感性を総動員してユーモアを発動させるわけです。ほかにもさまざまな手法が考えられますが、まずはその実例を見てみることにしましょう。
いまや『サザエさん』に引けを取らない国民的アニメとなった『ちびまる子ちゃん』の同名原作、漫画『ちびまる子ちゃん』の作者さくらももこ氏は、漫画のみならず数多くのエッセイを上梓しています。そのなかでも、老いも若きも賞賛を惜しまないのが第一作『もものかんづめ』です。まる子と同年代であった氏の少女時代にはじまり、その後のアルバイト生活やOL時代、さらにはデビュー後のエピソードを赤裸々に語った本書は、『ちびまる子ちゃん』に至る軌跡と原点までを網羅した、第一作にして集大成の趣さえあります。
17篇のエピソードを収める『もものかんづめ』。そのなかに上京後に住んだアパートで窓越しに露出狂と遭遇した、のちのちは笑えても当時は真剣に「恐怖」そのものであっただろうお話があります。さくら氏は実家の母に恐怖を訴え、母も母として娘に危険がおよばないよう必死に知恵を絞り、ある撃退アイテムを送って寄越します。それは、さくら氏の父が長年はき込んだ「パンツ」でした。
父の尻に敷かれ放屁に耐えてきたこのパンツ、これがいざという時の見張り番だと思うと自分の命の重さが100グラム位に思えた。
(さくらももこ『もものかんづめ』/集英社/1991年)
男性の下着を用いた変質者対策は定説の感ありですが、まずさくら氏本人がこれに思いおよばなかったことで、あれ? この人意外と純真だったんだな──と微笑ましさと親近感が湧きます。そしてこの短文には、氏独特のユーモア感覚がギュッと凝縮されています。解説しましょう。「パンツ」という語はいわゆる「下ネタ」。下ネタをトークに放り込みさえすれば、“ユーモア方面は万全”と信じ込んでいる向きは少なくないようですが、さくら氏のそれは一線を画しています。下ネタの常套句をあえて取り入れたこの一文に見るべきは、「父のパンツ(しかもはき古した)」と「自分の命の重さ」を並べて考えた点でしょう。「100グラム」は実に男物パンツの物理的重量だと思い至り、読み手の脳裏には、左の皿に父のパンツ、右の皿に自分の命の重さを載せ、ピッタリと釣り合おうとして揺れる上皿天秤の針のアニメーションすら浮かんできます。字面だけ見ればあからさまな下ネタなのに、鼻白むどころか共感と好感とほのぼのとした笑いを喚起する「一本」の技ここにあり──という一文なのです。
さて、ユーモアには「毒」が必要──というとある種の“狙い”が透けて見え語弊がありそうですが、これを丁寧に解説するとすれば、“毒を恐れない率直さをもつべし”というところでしょうか。『もものかんづめ』にはいささかの物議を醸したエッセイがあります。アニメで人気のじいさん「友蔵」と同名の祖父の死について語った「メルヘン翁」と題された一篇です。このなかでさくら氏は、実の祖父は作中のまる子と好ペアの友蔵とは似ても似つかぬ、家族の嫌われ者であったと明かします。その祖父がある日大往生を遂げたのでした。
「いい? ジィさんの死に顔は、それはそれは面白いよ。口をパカッと開けちゃってさ、ムンクの叫びだよあれは。でもね、決して笑っちゃダメだよ、なんつったって死んだんだからね、どんなに可笑しくても笑っちゃダメ」と(私は姉に)しつこく忠告した。
姉は恐る恐る祖父の部屋のドアを開け、祖父の顔をチラリと見るなり転がるようにして台所の隅でうずくまり、コオロギのように笑い始めた。
(同上 ※カッコ内は本稿筆者加筆)
本作の発表当時、このような調子で祖父の死を扱ったことで、さくらももこってこんな人だったんだと失望したファンも少なくなかったそうです。しかし現実問題、たとえ祖父とはいえ大嫌いであった人物の死に接し、マザーテレサでもないはずの人間が深く悲しみ嘆くものなのでしょうか。そんなときはたいてい、悲しみを帯びた(と思われるような)素振りを見せるか、安全地帯となった此岸から彼岸を遠望し達観したふうのひと言でも呟いてみせるか、あるいは自身の感情の吐露やエピソードに触れること自体を避けるのではないでしょうか。でもさくら氏は、そのどれにも該当することのない行動を取ります。公に発表するエッセイだからと飾るわけでもなく、偽悪の毒を意図するでもなく、ただただ“高校2年生だったその当時のおかしく感じた事実”を率直に伝えるだけなのです。
私は自分の感想や事実に基づいた出来事をばからしくデフォルメすることはあるが美化して書く技術は持っていない。それを嫌う人がいても仕方ないし、好いてくれる人がいるのもありがたいことである。
(同上)
こう語るさくら氏の一文はどこまでも清々しいものがあります。万人受けする話題などそうそうあるはずもないのですから、人の反応を徒に気にしても致し方なく、反感を恐れて毒気ある真実をオブラートに包んでもユーモアは生まれてきません。『もものかんづめ』で取り上げられているエピソードは、どれも誰もが経験するような日常の出来事。エッセイを書きたいと思うのならば、あなたが学ぶべきはそれを“ばからしくデフォルメ”する精神と手法、そして書きはじめると同時に眼の端にチラつく「仮想読み手」の良識に囚われない気概といえるのかもしれません。
いかがでしょう? このように考えれば、少し気も楽になりいくらかの勇気も湧いてくるというものではないですか? 今夜の夕食後にでも、おもしろエッセイをひとつ書いてみようかな──と思ってくださればうれしいです。
※Amazonのアソシエイトとして、文芸社は適格販売により収入を得ています。
2024/08/23
3
いま私小説を書くなら「露悪」や「破滅」は忘れておきたい 以前、当ブログ記事『「小説」をいかに読み、いかに書くか』では、“私小説を制する ...
2023/11/21
3
「ベタぼれ」でいい、けれどそれだけではもの足りない 犬ってかわいいですよね。もちろん犬だけではありません。「猫可愛がり」なんて言葉が辞 ...
2023/06/19
3
小説を書くのは小説を読んだから──の回答に秘められた重要な鍵 いきなりですが、あなたがもし「小説家になりたい!」と日夜創作に向かってい ...
2023/06/12
3
現代の徒然なる日記──ブログ そのむかし、人は秘められた思いを日記に綴ってきました。そう、大正・昭和の文学青年も、純情可憐な恋する少女 ...
2026/01/22
6
真の「希望」の在り処とは 学術的な見識のないままに推測で申しあげますが、「希望」や「絶望」を人間と同じように、単なる感情ではなく高次に ...
2026/01/14
6
哲学的テーマが宿命的創作テーマである理由 「人生とは自転車のようなものだ」と言ったのは、物理学者のアルバート・アインシュタイン。生きて ...
2025/12/23
6
「常識」という名の「情報操作」 「移民」と題したとおり、前回の「作家が「移民問題」に目を向けるとき」に引きつづき、移民問題をテーマとし ...
2025/12/22
6
作家を志す者と社会問題の関係性 近年、喧しくもちあがる社会問題のひとつに移民問題があります。やはり、長大な歴史の結果として“いまに帰着 ...