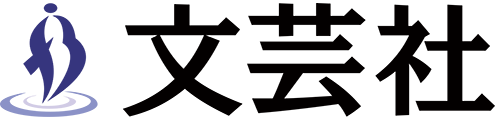�{���́u�̋��v�Ƃ́A�S�ɖ������
���������Y�̍ȁE�q�b�q�́A�����ɂ͖{���̋Ȃ��A�̋��̎R�̏�ɂ���{���̋\�\�ƊS�Q�����悤�ł����A�m���ɁA�ǂ�����Ɨ��������낷�R�̎p�́A�̋��̏ے��I���i�̂ЂƂ��v�킹�܂��B�����ɐ��܂������l�́A��⎩�}�̊܂݂��������āu�̋����Ȃ��v�ȂǂƂ����Ԃ����Ƃ�����悤�ł��B����ǁA�{���ɂ����ł��傤���B�N�ɂ��c�����オ�������悤�ɁA�N�����u�̋��v�������Ƃ��\�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�u�̋��v�Ƃ͂Ȃɂ��A����e�����n�Ƃ͌���Ȃ��͂��ł��B
�ӎ����Ȃ��܂܂ɐS�ɍ��Â��Ă������ݐ[���L���B�����ɂ͑N�₩�Ȍ̋��̕��i���L����A��ƂɂȂ肽���Ǝv�����Ȃ��̌��_��������Ă��邩������܂���B
�u�����鏬���̃��[�c�v���`���o���A��Ƃ̌����i
�}�[�N�E�g�E�F�C���͂��킸�ƒm�ꂽ�A���E�I�ɗL���Ȗ`�������w�g���E�\�[���[�̖`���x�Ɓw�n�b�N���x���[�E�t�B���̖`���x�̒��ҁB1835�N�A�A�����J�������̃~�Y�[���B�ɐ��������܂����A1840�N�A��Ƃ͓암�̃~�V�V�b�s�B�n���j�o���ɓ]�����܂��B4����߂������~�V�V�b�s�쉈���̂��̒n���A�}�[�N�E�g�E�F�C���ɂƂ��Ắu�̋��v�Ƃ����܂��B�����āA�ނ̑�\��2��i�̎�l���A�g���ƃn�b�N�����镨��̕���w�i���o��l�����A�n���j�o���Ƃ����ɕ�炷�Z�l���������f���ɂȂ�܂����B
�^���͏�������Ȃ�B�Ȃ��Ȃ�A�t�B�N�V�����͉\���������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�^���͂����ł͂Ȃ��B
�������FTruth is stranger than fiction, but it is because Fiction is obliged to stick to possibilities; Truth isn�ft.�iMark Twain�wFollowing the Equator�x/1897�N�@�F�}�[�N�E�g�E�F�C���w�ԓ��ɉ����āi��E���j�x�ʗ���/1999�N�E2000�N�j
��҂̏��N����̎����ɍ������A�n�b�N���~�V�V�b�s�������Ȃ���Љ�̌�����ڂ̓�����ɂ��Ă����w�n�b�N���x���[�E�t�B���x�̃X�g�[���[�B����͗D�����L���Ƃ͌���܂���B�g�E�F�C���̌��t�ǂ���A�Ƃ��Ɍ����Ƃ͊�]�Ȃǂ���������������Ȃ����c�Ȃ��̂�����ł��B����ǂ��A�g�E�F�C�������ݏo�����`������́A�����̂��肳�܂��f���o���Ȃ���A�`���̐�ɂ��関�m�̐��E���w�������Ă��܂��B�A�[�l�X�g�E�w�~���O�E�F�C�́A����ȁw�n�b�N���x���[�E�t�B���̖`���x���A�u�����錻��A�����J���w�́A�}�[�N�E�g�E�F�C���́w�n�b�N���x���[�E�t�B���x�Ƃ�����������ɔ�����v�ƁA�A�����J���w�j�̐��Ƃ��ċP�������ʒu�Â����̂ł��B
�̋��ɉ萁��������̑�Ȏv�z
�����l�̐��_���������悤�ƁA��w�ւ̎u���̂ĕ��|�^�����N�������D�v�B���̒����Ȏv�z�Ƃ��A����̋A���̌������Ƃɕ`�����Z�ҏ����w�̋��x�́A����߂��v���o����������y�n���A�g�����ʂɂ���ĕς��ʂĂ����Ƃւ̎��ӂƔ߂��݂ɖ����Ă��܂��B��l����20���N�Ԃ�ɋ����֖߂�A���̍r���i�ɂ��Ƃ��悤�̂Ȃ��̂������o���܂��B�S�̂��ǂ���ƂȂ�s�ς̎p�����������̋��B�ނ͂��̍r�p�̌������������܌��܂��B���Ԃ̗���̂����ł��Ȃ���A���̕ω��̂��߂ł�����܂���B����́A�l�Ԃ̂����ł����B���N���̖Y�ꂪ�������Ԃ��Ƃ��ɂ����c�Ȃ��݂�����ς��Ă��܂����A�u�Љ�v�̂����������̂ł��B
�u�U�ߗl�v�ƈ�n�b�L���������B�킽���͂����Ƃ��Đg�k�����o�����ɂȂ����B�Ȃ�قǂ킽���ǂ��̊Ԃɂ͂��͂�߂��ނׂ��u�Ă��o�����̂��Ǝv���ƁA�킽���͂����b���o���Ȃ��B
�i�D�v�w�̋��E��Q���`�x������/2009�N�j
�ڋ��ɓ��𐂂��c�Ȃ��݂ɁA��l���͌̋����������悤�Ȏ₵���𖡂킢�܂����B�������A��l���͑ł��Ђ������݂̂ł͂���܂���ł����B�D�v�͂��̍�i�ɐ�]��`�����킯�ł͂Ȃ��̂ł��B����̏I�ՁA�c�Ȃ��݂̑��q�Ƃ̍ĉ�������l���̉��̎p��`���Ă݂����悤�ɁA�w�̋��x�͘D�v�������グ�邻�̎u��\��������i�ƌ��邱�Ƃ��ł���̂ł��B
�v���Ɋ�]�Ƃ́A���Ƃ��Ƃ�����̂Ƃ������ʂ��A�Ȃ����̂Ƃ������Ȃ��B����͒n��̓��̂悤�Ȃ��̂ł���B���Ƃ��ƒn��ɓ��͂Ȃ��B�����l�������Ȃ�A���ꂪ���ɂȂ�̂��B
�i���j
�u���v�Ƃ͐l��������́A�S�ƕ���������l�X�ɂ���Ăł���������́\�\�w�̋��x�̃��X�g�ŘD�v�͂������_�Â��܂��B�K�����x�����R�Ƒ��݂���Љ�A���ʂɊÂ�l�Ԃ̔ڏ��B�w�̋��x�ɂ́A�܂肻���Ɉق�������D�v�̎v�z�̌��_������A�ނ͌̋��ɘȂގ����̎p����A�����ƒ����l�̖����ւ̎u��V���ɂ����ɈႢ����܂���B
70�N�̐l���̑b�ƂȂ������N����̑̌�
�u���{�����w�v���m�����������w�ҁE��Ƃ̖��c���j�́A���Ƃ��u����̖����w�̌��_�v�Ƃ��āA���N����̐_��I�ȑ̌����w�̋����\�N�x�Ƃ������ɒԂ�܂����B���c���̋��̕��Ɍ��̒Ґ쑺�i���E�_��S���蒬�j�ŕ�炵���̂́A10�N���������̒Z�����Ԃł������A����10�]�N�������̂���70�N�̐l���̊�ՂɂȂ����ƁA�ӔN�ɏ����ꂽ�{���̃^�C�g���͒m�炵�߂Ă��܂��B
���̉Ƃ͓��{�ꏬ�����Ƃ��B���́A���̉Ƃ̏������Ƃ����^�����玄�̖����w�ւ̎u���������Ƃ����Ă悢�̂ł���B
���̐S�g���������čs���ɂ�A���̊Ⴊ�S���I�Ɋg����A���E���̂��Ƃɂ��S���������悤�ɂȂ������Ƃɕs�v�c�͂Ȃ��B����������ł��c�����̎��ƁA���̎����߂�����͂̓����Ƃ͔��\�]�̍����Ȃ��܂��܂��ƋL���ɗ����ď����邱�Ƃ͂Ȃ��B
�i���c���j�w�̋����\�N�x�u�k��/2016�N�j
���|�]�_�ƁE���яG�Y�́A�u���t�ɂȂ�ʎ��R�Ƃ������݂ɖʂ��Ă���̂����A���̒��ڂȌo�����A���t�ɐ���ʂƂ������̎����A�ނɕ\�������߂Ď~�܂Ȃ��̂ł��v�i�w���яG�Y�S��i26�@�M���邱�Ƃƒm�邱�Ɓx�V����/2004�N�j�ƁA���c�̎��R�ɓ�����鍰�̂�����������A�ނ����̖����w�҂Ȃ炵�߂��ƌ��܂����B�w�̋����\�N�x�ɂ́A�c�����ɕ�炵���R���Ŗ��c���g���o�������A���X�̕s�v�c�ȃG�s�\�[�h���Ԃ��Ă��܂��B�܂�A���R�̐_���̊����A�����̋L����厖�ɑ厖�ɋ��ɕ����Â����A���̖L���Ȋ����������c�̖����w�̃��[�c�ł���Ƃ������ƂȂ̂ł��B
�ǂ����Ă��������̂����ł��킩��Ȃ����A���͂��Ⴊ�܂܂悭�ꂽ������グ���̂������B����Ƃ����邪������̂��B�����N�₩���S���Ă��邪�A���ɐ��ݐ�����ŁA�����ɂ������ɝɏ\�̐��������̂ł���B��Ԍ����Ȃ��͂������Ǝv���āA�q���S�ɂ��낢��l���Ă����B���̂��돭�����莄���V���̂��Ƃ�m���Ă����̂ŁA�����댩����Ƃ����玩����̒m���Ă��鐯����Ȃ�����A�ʂɂ������܂��K�v�͂Ȃ��Ƃ��ӐS�������߂����B
(��)
�u�̋��v�ɖ���A�{�������������Ȃ��̎u�ƃe�[�}
���Ɍ����鐯�A����͂ӂ�����Ɍ�����̂Ƃ͂܂��ʂ̐��A�ƂЂƂ育�������c���N�́A�₪�ē��{�����w��n�n���܂��B
���m�̂��̂������_�炩�������ȐS���A�������͐�������ǂ����Ŏ����Ă��܂��̂ł��傤���B����Ƃ��A�S�̗��̌����Ȃ��Ƃ���ɏ������ƂȂ����点�Ă���̂ł��傤���\�\�B
�{�����������Ǝu���Ȃ�A���炩�ɖڂ���āA���̔閧�̋L���̈���Ăъo�܂��Ă݂܂��B���̂Ƃ��ɐG�}�ƂȂ�̂��u�̋��v�̑��݂ł��B�c�����̕��i�A�����ŗV�F�̎p�A���̂悤�ɕs�v�c�ȏo�����A���R�̍��C�c�c�B�̋��̋L���ɂ́A��ƂɂȂ肽�����Ȃ��̓��W���ԈႢ�Ȃ�����Ă���͂��Ȃ̂ł�����B
��Amazon�̃A�\�V�G�C�g�Ƃ��āA���|�Ђ͓K�i�̔��ɂ������Ă��܂��B