本を出版するなら─文芸社。「出版」のこと、気軽にご相談ください。
平日9:30〜18:30通話無料
0120-03-1148問い合わせ
検索
書籍検索
フリーワード検索
ジャンル検索
小説
エッセイ
童話・絵本・漫画
画集・写真集
教育
実用
語学
社会
ビジネス
医学・健康
看護・闘病
伝記・半生記
歴史・戦記
詩集
俳句・短歌
地理・紀行
自然・科学・工業・学術
哲学・心理学・宗教
芸術・芸能・サブカルチャー
スポーツ
雑誌・学参・その他
本を出版するなら─文芸社。「出版」のこと、気軽にご相談ください。
平日9:30〜18:30通話無料
0120-03-1148問い合わせ
検索
書籍検索
フリーワード検索
ジャンル検索
小説
エッセイ
童話・絵本・漫画
画集・写真集
教育
実用
語学
社会
ビジネス
医学・健康
看護・闘病
伝記・半生記
歴史・戦記
詩集
俳句・短歌
地理・紀行
自然・科学・工業・学術
哲学・心理学・宗教
芸術・芸能・サブカルチャー
スポーツ
雑誌・学参・その他
Blog
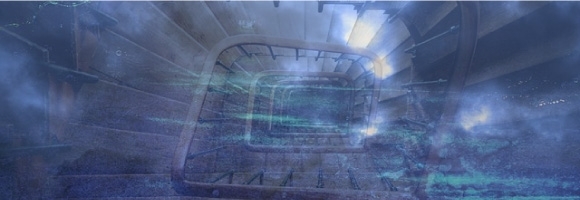
詩を書くためには、いうまでもなく詩句(≒言葉)が不可欠です。詩人になりたい、と志しているあなたがもしもここで、そんなことは当たり前、何を今さら……と「≒」記号を軽く受け流したとしたら、要注意のサイン。「“詩の言葉”に対する意識が甘ーい!」といわざるを得ません。とかくいまの世、周囲には文字や言葉が溢れかえっています。ラインにメールにツイッター。あまりに軽々しく不用意に扱われている感すらあります。しかしながら、巷間に氾濫する“それらの言葉”と“詩の言葉”は似て非なるもの――というか根幹ではそもそもまったく別ものなのです。そういう意味では、「≒」ですらなく「≠」と表記すべきかもしれません。そのくらい、詩を書くための言葉とは、ふだん私たちが何気なく使う言葉と比べ遥かに重大かつ深遠であるはずのものなのです。
詩人の詩句に対するこだわりは、それこそ余人の想像を絶するといっても過言ではありません。北杜夫は高校生だったころ、土手に座り込んで歌づくりに何時間も呻吟している父・齋藤茂吉の姿を見て、初めて歌人としての父に対する尊敬の念を覚えたと語っています。詩人の山之口貘は、一篇の詩を書きあげるまでに100枚も200枚も推敲し、たったひとつの言葉に至るまで練り上げました。実のところ、詩なりコピーなり文章を考えているときにポッと頭に浮かび、こりゃ名文句だワと書きつける類の言葉は、大抵が後年に自らの頬を赤く染める、ただの上ッ滑りな駄文に過ぎなかったりします。文字による表現はそれこそ無限ですが、一篇の詩の特定箇所にぴたりと当てはまるのは、詩人の血の滲むような芸術的格闘の末に現れてきた言葉だけなのです。
詩は自由な言葉で表現してよいもの――確かにそうかもしれませんが、ともするとここには誤解が生じることもあります。詩の言葉とは、自由であっても厳密なものだからです。もっと正確にいうならば、“本物の自由”を備えていなければなりません。流行り廃りに影響されていたり、読者におもねってみたり、独りよがりだったり、似非自由の悪臭を漂わす詩ほど読み手をゲンナリさせるものはありません。たとえば、斬新な表現のつもりで「空を掘る」などと表現してみても、書き手と読み手のあいだにシンパシーは生まれにくいでしょう。「雨は私の悲しみを洗い流してくれる」に「川が流れて海に注ぎこむように」とつづけたとしたら、この直喩は明らかに不自然でしょうしあまりにも陳腐です。詩人の言葉に対する、まるで小姑のような厳格さを表すエピソードにも事欠きません。たとえば、三好達治は大岡信のある詩について大変手厳しい批評を述べました。
国文畑の出身と聞く作者が、「鳥たち」「花々」などといふのは、もと、変てこな語感に違いない。意味のアイマイなだけ、音調においてはするすると滑りのよい、それらの比喩、…それらは、かんじんの「詩」の犠牲に於て、その「突貫工事」を突貫しようとするのであらうかと…
いまでこそ「鳥たち」や「花々」はそこかしこに見られる表現ですが、確かに本来日本語の名詞は複数形をもたないものでした。もっとも、当時にしても「鳥たち」くらい用いる詩人はほかにもいたとは想像されますが、三好達治はこの一事を取っ掛かりにして大岡のこの詩の弱さに踏み込んでいったのでしょう。ある意味で詩人は、こうした手練手管、魑魅魍魎による批評に常に晒されているわけです。それに対し逃げも隠れもせず真剣勝負の気迫で対峙するのが、詩人のあるべき姿なのでしょう。
まずことばの生理を知らなくてはならない。例えばどんな言葉にもその時点における質量がある。概念というか、ことばのそれは時々刻々とグラム単位で変化しているわけですね。そこをつねに計算に入れておかなくてはならない。それがことばというものです。あと、このAということばにBということばを続ければ意味合い色合いはどうなるか、どんな温度変化をきたすかというような展開(感覚)、行間の化学変化にも当然つよくならなくてはならない。
(荒川洋治『詩とことば』岩波書店/2012年)
詩人・随筆家の荒川洋治は、今日の詩の書かれる道を拓くべく詩論『詩とことば』を著しました。詩の言葉は生活のなかに無数に溢れている。人はその言葉によって人と繋がり、自分自身を生きていく。生活のなかに存在する言葉を、詩の言葉として命を与える――そうした詩作の営みとは、新しい世界に開眼していくことであると荒川は語っています。
次に挙げる詩の作者はシベリア抑留体験を詩のテーマとして確立させた、戦後詩壇を代表するひとり、石原吉郎。荒川洋治が『詩とことば』で取り上げた詩人です。
かなしいかな月明なのだ
桶の底まで月明なのだ
夜陰に乗じた馬の
蹄のうらまで月明なのだ
藁の人形を大地へ伏せて
細い刃もので
まふたつにしても
影が左右にあるかぎりは
かなしいかな
月明なのだ
(後略)
(石原吉郎『月明』/『石原吉郎全集 第1巻』所収/花神社/1979年)
穏やかな光で地上を照らす“月明かり”を詠った詩ですが、ここには慈愛も優しさも心のなごみもなく、ふと月を見上げた者を取り巻いていた悲痛な記憶があるばかりです。キリスト教者であった石原は、8年に亘る俘虜生活から帰還後、心を苛む疑問の答えを信仰に求めたことでしょう。しかし、求めて得られない答えは自ら探すしかなかった、その手段が詩作であり、石原の生きる道でした。
詩のことばは、個人の思いを、個人のことばで伝えることを応援し、支持する。その人の感じること、思うこと、体験したこと。それがどんなにわかりにくいことばで表されていても、詩は、それでいい、そのままでいいと、その人にささやくのだ。石原吉郎の詩は、そうした詩のことばの「思想」によって支えられ、生きつづけることができた。
(同上『詩とことば』)
「思想」とはつまり作者の、詩の言葉を紡ぐための内的モチベーションと言い換えられるでしょうか。もちろん、モチベーションが凄まじく強烈であれば優れた詩が生まれるというわけではありません。しかし、そもそも現代詩とは、外界と対立する自己の内面を表現するもの。ですから、その言葉が不用意なもの、安易なものであることなどあり得ません。言葉に「思想」があるからこそ、詩は命を得ることができる――荒川洋治はそう言っているのです。
詩の言葉は、思考やイメージのなかから生まれてくるものです。詩人・吉野弘は「創造」の「創」には「きず」という意味があり、ものごとのはじまりが「きず」であるということは非常に意味深いと考え、「きず」からはじまるさまざまな創生の事象を詠い『創』という詩を書きました。前出の石原吉郎は、あるとき、ふと目にした壁に優しい人の背中のくぼみがある、という発想を得ました。それからそのイメージを詩に昇華させる術をもたぬまま数年が過ぎたある日のこと、不意に浮かんだ「フェルナンデス」という言葉から、長らく静止したままであったイメージは俄かに動き出して『フェルナンデス』という一篇の詩ができあがったのでした。石原はこのように詩の言葉に出会った瞬間について、「ことばに出会うという機縁の不思議さ」を痛切に感じる、と述べています。
絵画に喩えるなら、詩はいってみれば“言葉”で描く芸術です。ひとつひとつの言葉が一枚の絵のディテールであり、ひと筋たりとも揺るがせにはできないものです。詩を書いているあなた、会心の一作を書こうと日々ペン先を舐めているあなた。たまには前を見るばかりでなく、自分がこれまで詩の言葉をどのように扱ってきたかを振り返ってみてもいいはずです。言葉は、文字に結びついた意味の向こうに、果てしなく広がった世界をもっています。その世界は、詩人の思い描くイメージや思想へとつながっています。自身の内面に広がる宇宙を覗き見ることができたとき、瞬く間にあなたの詩想はかつてない空間性をもって眼前に迫ってくることでしょう。
※Amazonのアソシエイトとして、文芸社は適格販売により収入を得ています。
2025/12/10
7
「自然」をどう捉え、詠うべきか レオナルド・ダ・ヴィンチしかり、バートランド・ラッセルしかり、国内に目を向ければ、南方熊楠しかり……と ...
2025/07/10
7
「人生」と「文学」の最重要エレメント──革命的思想 革命──それはかつて、理想を胸に抱く、わけても純粋な青年たちの血と精神を滾らせる言 ...
2024/09/05
7
「師」として漱石が照らした道 夏目漱石が教職に就いていたことはよく知られていますが、根のところでも極めて秀でた「師」としての資質を湛え ...
2024/05/20
7
人間は愚かなり 種々の欲望に振りまわされ、煩悩に心を挫く人間。その愚かさや不完全さは、多少の差こそあれすべての人間がもちあわせているも ...
2026/01/22
6
真の「希望」の在り処とは 学術的な見識のないままに推測で申しあげますが、「希望」や「絶望」を人間と同じように、単なる感情ではなく高次に ...
2026/01/14
6
哲学的テーマが宿命的創作テーマである理由 「人生とは自転車のようなものだ」と言ったのは、物理学者のアルバート・アインシュタイン。生きて ...
2025/12/23
6
「常識」という名の「情報操作」 「移民」と題したとおり、前回の「作家が「移民問題」に目を向けるとき」に引きつづき、移民問題をテーマとし ...
2025/12/22
6
作家を志す者と社会問題の関係性 近年、喧しくもちあがる社会問題のひとつに移民問題があります。やはり、長大な歴史の結果として“いまに帰着 ...
2025/12/10
7
「自然」をどう捉え、詠うべきか レオナルド・ダ・ヴィンチしかり、バートランド・ラッセルしかり、国内に目を向ければ、南方熊楠しかり……と ...