本を出版するなら─文芸社。「出版」のこと、気軽にご相談ください。
平日9:30〜18:30通話無料
0120-03-1148問い合わせ
検索
書籍検索
フリーワード検索
ジャンル検索
小説
エッセイ
童話・絵本・漫画
画集・写真集
教育
実用
語学
社会
ビジネス
医学・健康
看護・闘病
伝記・半生記
歴史・戦記
詩集
俳句・短歌
地理・紀行
自然・科学・工業・学術
哲学・心理学・宗教
芸術・芸能・サブカルチャー
スポーツ
雑誌・学参・その他
本を出版するなら─文芸社。「出版」のこと、気軽にご相談ください。
平日9:30〜18:30通話無料
0120-03-1148問い合わせ
検索
書籍検索
フリーワード検索
ジャンル検索
小説
エッセイ
童話・絵本・漫画
画集・写真集
教育
実用
語学
社会
ビジネス
医学・健康
看護・闘病
伝記・半生記
歴史・戦記
詩集
俳句・短歌
地理・紀行
自然・科学・工業・学術
哲学・心理学・宗教
芸術・芸能・サブカルチャー
スポーツ
雑誌・学参・その他
Blog
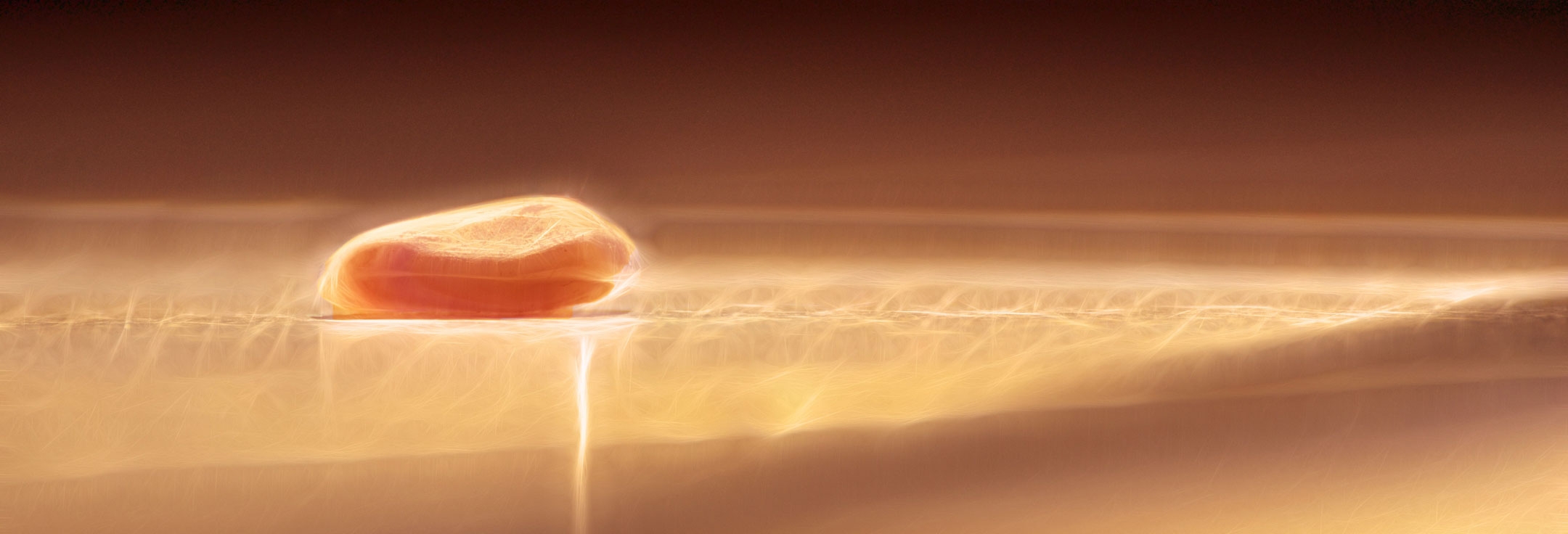
「全身詩人」という有無をいわせぬ異名をもつ現代詩壇の巨星、吉増剛造。それは文字どおり、全身全霊で詩作に打ち込み、その血も肉も「詩」でできているというような、詩の申し子という意味でしょう。この、凡人なら尻込みするであろうたいそうな名「全身詩人」をものともせずに背負い、というか、詩人に名が必死に追いつこうとさえしているような印象にこそ、吉増剛造の吉増剛造たる所以があります。実のところ、これほど激しく突出した個性を有する表現者となれば、詩人になりたいと純粋な希望で胸ふくらませる作家の卵が、知識や作法(さくほう)の面で学び盗んで活用できることなどほとんどないのかもしれません。が、もとより吉増剛造に学ぶべきは知識や技術ではありません。作家の卵が吉増剛造に学ぶべきは、もっと原初的で、もっと雄大なこと。つまり、詩という宇宙と交感する感覚を知ることです。
「全身詩人」である吉増剛造は、詩を従来の詩表現世界に留めず、無限の詩的インスピレーション閃くまま、朗読、音楽、写真、映像、絵画、オブジェと縦横無尽にアートの海に漕ぎ出でてきました。それは偏狭な眼差しでは決して捉えることのできない詩の世界。一足飛びに行き着くことは不可能な高みです。けれど、吉増剛造という人物の、ひとりの人間としての存在にフォーカスすれば、彼にも通過点があり、原点があったことは間違いないはず。宇宙の彼方の巨星がいきなり地上に降り立ったわけではないのです。では、たとえ当人としては意識していなかったとしても、本能的に、感覚的に、彼がもちつづけた原点とは何でしょうか。それは、吉増自身が後年あらためて噛みしめたという、フランスの詩人ポール・ヴァレリーの「詩というのは、言葉と音の間のような微妙な所にあるものだ。意味だけではない」の言葉に現れているように感じられます。彼の詩業を遡って辿ることで、この言葉の具体的な意味が見えてくるかもしれません。
アリス、アイリス、赤馬、赤城、――
イシス、イシ、リス、石狩乃香、――
兎! 巨大ナ静カサ、乃、宇!
ルー、白狼、遠くから、かすかに、本当の声が、聞こえて来て居た、、、
(吉増剛造『詩の傍(cotes)で』より/『怪物君』所収/みすず書房/2016年)
吉増がヴァレリーの言葉を思い返したきっかけは、東日本大震災だったといいます。これを機に、30年来つづけきた日記を彼はやめます。日記というものに「制度」の虚しさを感じたからでした。そして吉増は、であれば詩も、「詩の制度」から抜け出すべきではないかと考えたのでした。その沈黙のなかから誕生したのが、詩集『怪物君』です。この詩集に触れてみると、言葉と音がぶつかりあい破壊されたのちに、いつしか届けられるものがあることに気づきます。それは、意味を伴わない、音や叫びや心の振動というような無形の現象が伝える「本当の声」というべきもの。『怪物君』は進化、前進しつづける詩人のひとつの到達点を示す記念碑ですが、この詩集に至る歳月に、吉増剛造という詩人の確かな足跡が現れてきます。
“ウオゴス”の一語(いちご)で“苺が、・・・・・・”蘇った、次の日の朝
Doubletree、朝露に濡れた“あたらしい記憶の丘”に
挨拶をする。u、o、e、も“ひらなが”のようですと
なんだろう、この“ひらなが”、・・・・・・
(『わたくしたちは何処まで行くのだろうかもう果しがない気がしていた』より/『「雪の島」あるいは「エミリーの幽霊」』所収/集英社/1998年)
ご存じのとおり、詩はしばしば韻を踏みます。上の吉増の詩も押韻の技法が用いられています。しかし、いくつもの決まりごとや名目のあるこの伝統的な技法にあって、吉増の韻語は何にも束縛されず自由で、それらは読む者を驚かすとともに自由な読み方を求めてきます。脳が痺れんばかりのこの言葉の連なりを、地球外生物の書物をうっかり開いてしまった学者のように、眉根に思い切り皺を寄せて凝視するのはばかばかしいことです。詩とは、断じてそんなふうに味わうものではないはず。見たこともない景色を映し出す詩であれば、なおのこと未知の空間を散歩するように味わいたいところです。何の訓練も受けぬまま地上を飛び立ち、成層圏を突き破り、宇宙服も着ずに月面を闊歩する感覚でよいのです。
吉増の代表的詩集のひとつ『黄金詩篇』は、およそ50年前に出版されました。そのなかには、まだ若い20代の吉増剛造がいます。
ぼくの意志
それは盲る(めしいる)ことだ
太陽とリンゴになることだ
似ることじゃない
乳房に、太陽に、リンゴに、紙に、ペンに、インクに、夢に! なることだ
凄い韻律になればいいのさ
(『燃える』より/『黄金詩篇』所収/思潮社/1970年 ルビは引用者による)
ぼくは詩を書く
第一行目を書く
彫刻刀が、朝狂って、立ちあがる
それがぼくの正義だ!
(中略)
アア コレワ
なんという、薄紅色の掌にころがる水滴
珈琲皿に映ル乳房ヨ!
転落デキナイヨー!
剣の上をツツッと走ったが、消えないぞ世界!
(『朝狂って』/同上)
『燃える』と『朝狂って』は対を思わせる2篇で、青年(あるいは少年)「ぼく」の詩作への輝かしき意気込みを高らかに詠っています。無邪気さを思わせるような一風ユーモラスであけっぴろげな詩語ですが、意味をなすようでいてなさない「言葉」と「音」のあいだから、「詩」を浮かび上がらせる明確な意識が覗いています。『朝狂って』の冒頭、勢い込んで「詩を書く」と明言する「ぼく」ですが、以降描かれているのは、いわゆる詩を書いているのとはまるで違う姿です。それでも「ぼく」が、燃えるように、朝から狂っているかのように、何にも邪魔されずどんな試練にも屈しない覚悟で、詩の道へと果敢に突き進もうとしているのだとわかります。
「芸術は爆発だ!」と岡本太郎は言いました。派手なパフォーマンスから流行語のようにもなりましたが、実をいえば、吉増の詩作の姿勢と解釈はこの言葉にも通じています。創造・創作の要素がぶつかりあった破壊や爆発のなかに、別の意味と成果が生まれてくるというのが、芸術のひとつの真理なのかもしれません。それはちょうど、超新星爆発の副産物として未知の素粒子が発現するようなもの。詩人内部で行き交う分子の衝突で生じる厖大なエネルギーが、創作物に新たなる価値を賦与するのでしょう。詩を書きたい、詩人になりたいあなた。煌めく無数の星々が拡散していく宇宙の情景を思い描いてください。詩作とは、無限の広がりを秘めたそれほどに壮大な世界をつくりあげることなのです。
※Amazonのアソシエイトとして、文芸社は適格販売により収入を得ています。
2025/12/10
7
「自然」をどう捉え、詠うべきか レオナルド・ダ・ヴィンチしかり、バートランド・ラッセルしかり、国内に目を向ければ、南方熊楠しかり……と ...
2025/07/10
7
「人生」と「文学」の最重要エレメント──革命的思想 革命──それはかつて、理想を胸に抱く、わけても純粋な青年たちの血と精神を滾らせる言 ...
2024/09/05
7
「師」として漱石が照らした道 夏目漱石が教職に就いていたことはよく知られていますが、根のところでも極めて秀でた「師」としての資質を湛え ...
2024/05/20
7
人間は愚かなり 種々の欲望に振りまわされ、煩悩に心を挫く人間。その愚かさや不完全さは、多少の差こそあれすべての人間がもちあわせているも ...
2026/01/22
6
真の「希望」の在り処とは 学術的な見識のないままに推測で申しあげますが、「希望」や「絶望」を人間と同じように、単なる感情ではなく高次に ...
2026/01/14
6
哲学的テーマが宿命的創作テーマである理由 「人生とは自転車のようなものだ」と言ったのは、物理学者のアルバート・アインシュタイン。生きて ...
2025/12/23
6
「常識」という名の「情報操作」 「移民」と題したとおり、前回の「作家が「移民問題」に目を向けるとき」に引きつづき、移民問題をテーマとし ...
2025/12/22
6
作家を志す者と社会問題の関係性 近年、喧しくもちあがる社会問題のひとつに移民問題があります。やはり、長大な歴史の結果として“いまに帰着 ...